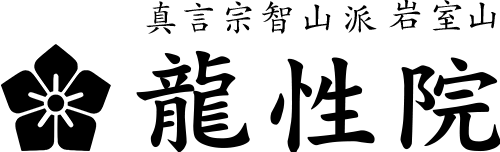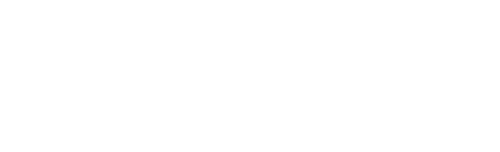-
正月号2015.01.01
新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
龍性院檀信徒の皆様方におかれましては、平成27年の新しい年をご家族ご一同様でご無事にお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。
また、昨年中に皆様方に賜りましたご厚情に対しまして、心よりお礼を申し上げます。
昨年1年を振り返りますと、2月に関東地方を襲った豪雪に始まり、夏には豪雨に伴う広島の土砂災害、9月には御嶽山の噴火、11月には長野県北部を中心に最大深度6弱を観測する地震が発生する等、日本は多くの自然災害にみまわれ、全国各地に甚大な被害をもたらしました。
しかし、悲しいことではありますが、このような災害は日本だけに止まらず、世界各地でも多数発生をし、多くの方々を苦しめる一因となっています。
過去の龍性院だよりでも申し上げましたが、仏教における自然観は、人間が自然を支配する、従属させるというものではなく、自然と共生する生き方を目指すものです。
言うまでもなく、このような悲惨な災害が無いに越したことはございません。
しかしながら、いつもは大いなる恵みを与えてくれるも、時には牙をもむくこの〝自然〟に、私たちが生かされているのは、厳然たる事実なのです。
〝自然〟とは元来、地球上のすべての生物に恵みを与えてくれる有り難いものではあるが、時には恐ろしい一面もあるとしっかりと認識をし、災害に対してできる限りの備えを致すことで、自然との共生を図っていくほか、道は無いのだと思います。
そして、そうした災害によって奪われてしまった尊い命が、少しでも安らかなるようにと鎮魂の祈りを捧げ、残された方々に寄り添い、再び前を向いて歩めるようお手伝いをしていくことが何より重要ではないかと、私は思います。
さて、昨年は災害が続いた日本ではございましたが、このような苦しい状況の中にも、一筋の光明をみた気が致しました。
8月に広島市で土砂災害が発生した折、東日本大震災の時に広島の方々に良く援助をして頂いたからとの理由で、東北地方から多くのボランティア団体が広島へ駆けつけ、救助に務めて下さったそうです。
ニュースを見ていると、凶悪犯罪が後を絶たないように思えるこの日本ですが、奪い奪い合うのではなく、施し施し合う仏さまの心が、まだまだ多くの人の心に根付いているのかなあと、少しだけ温かい気持ちになりました。
こういった施し合う仏さまの心を、私たちも見習い実践していきたいものです。
1月1日の早朝には、『今年1年が、生きとし生ける皆にとって安らかな年となりますように…』とご本尊不動明王さまにご祈念を申し上げたいと存じます。
年頭に当たり、皆さまのご健勝、ご多幸をせつにお祈りいたします。
-
お盆号2014.08.01
大切な人の仏様に
梅雨らしい、ジメジメとした湿度の高い日が続いております。
気象庁の発表によりますと、今年の関東甲信の入梅は6月5日で平年より3日、昨年と比べて5日ほど早かったそうです。
私個人と致しましては、多少暑くてもからっと晴れた天気が大好きなものですから、梅雨明けが待ち遠しい限りです。
しかし、自然に生かされていることを考えますと、雨の日も無くてはならないもので、この梅雨の時期は恵みの季節だとプラスに考えるようには努めておりますが・・・。
梅雨の時期の雨は、しとしとと降る長雨というイメージがありますが、今月3日には九州北部を中心に大雨に見舞われ、長崎市などでは実に50年に1度という記録的な豪雨となりました。
また、台風8号の接近に伴い、新潟県佐渡市でも50年に1度の大雨が降ったとのことです。
これらの影響で、日本各地で崖崩れや土砂崩れ、道路が冠水するなどの被害も出ているとのことです。
被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
さて、今年もあと1ヶ月たらずでお盆を迎えます。
お盆の期間中は、各家庭におかれまして精霊棚(盆棚)を飾っていただき、亡きご先祖様、仏様をお迎えしていただくわけでございます。
グローバル化が進む現代社会においては、お盆やお正月といっても仕事をゆっくりと休めない方も増えて来ていることでしょう。
しかし、日本では古くからこのお盆の期間中は、ご先祖様が家に帰って来て下さり、生存している私たちが亡くなった方といっしょに過ごすことができる1年に1度の機会だと信じられております。
できることならば、お盆期間中は家にいる時間を増やし、自分自身のルーツであるご先祖様を身近に感じていただきたいと思います。
人間を含め、ありとあらゆる生き物は、死んだらすべてが“無”になると考える方もいらっしゃいます。
ですが、私たちの祖先はそのようには考えていなかったのだと思います。
私自身も先代の住職であった父を亡くしております。
今年の11月になりますと丸9年という月日が経過を致しますが、今でも仏壇に向かって線香をお供えした時、墓地にお水をかけている時、写真を眺めた時、はっきりと心の中にその姿が思い出されます。
少し悩み事がある時には、父ならこんな時どう行動するのかと自分の心の中で考え、相談をしたりします。
何か良いことがあった時には、仏壇に向かって報告をしたりもします。
また、生前の父と知己であった方から、「本当にいい人だったねぇ」などと声をかけていただき嬉しい気持ちにもなったりします。
亡くなっているはずの“父”が、今を生きている“私”の考え方、行動などに深く影響をしているのです。
これは、少なくとも“無”になっているとは考えられません。
例え自分は死んでしまっても、残された大切な者の心の中ではいつまでも生き続ける、それが仏様になることなのだと私は思います。
私たちの祖先も、細かい考えの違いはあれど、亡き後は決して“無”になるのではなくて、何らかの形でこの世に関連し自らの存在というものが残っていくと考えたのではないでしょうか。
ですから、いつかわからないが必ずやってくる『死』を前にして、1度の人生を欲望のまま生きるのではなく、自分の為にも、周囲の為にも、悔いの残らない人生を歩むことが大事なのです。
そうすることで自分の亡き後、大切な人の心の中を常に照らし、励まし、背中を押していけるような仏様になれるのだと思います。
自分の大切な人が、仏様に励まされ心豊かに生きていけたら、すごく嬉しいですよね?
これから迎えるお盆を機に、今1度ご先祖様について、仏様について、自らの生き方について考えていただけたら幸いです。
日本列島に被害をもたらした台風も過ぎ去り、今年の夏も、例年通りの暑い日々が続くものと予想されます。
龍性院檀信徒の皆様方におかれましては、くれぐれも体調管理には気をつけていただき、ご健勝にてお過ごしくださいますよう、お願い申し上げます。
2 -
正月号2014.01.01
新年を迎えて
龍性院檀信徒の皆様方におかれましては、平成26年の新しい年をご家族ご一同様でご無事にお迎えのこと、心よりお慶び申し上げます。
また、昨年中に皆様方に賜りましたご厚情に対しまして、心よりお礼を申し上げます。
さて、當山龍性院の境内地から約600メートル程離れたところに、龍性院の境外(けいがい)仏堂(ぶつどう)である〝岩室(いわむろ)観音堂(かんのんどう)〟がございます。
この岩室観音堂とは、真言宗の宗祖、弘法大師空海が岩窟を選んで高さ一尺一寸(36.4㎝)の観音像を彫刻してこの岩窟に納め、その名前を岩室山と号したものが始まりであると伝えられています。
現在のお堂は松山城の落城とともに焼失したものを江戸時代に再建したものと言うことであります。
この岩室観音堂の1階には、左右に岩室があり88体の石仏が祭られております。
この88体の石仏は、四国八十八ヶ所弘法大師巡錫の霊地に建てられた寺々の本尊を模したものであり、この石仏をおがめば、四国八十八ヶ所を巡拝したのと同じ功徳があるとされています。
長々と説明を申し上げてしまいましたが、昨年(平成25年)10月、この石仏の内の5体の石仏が、何者かに破壊をされるという事件が発生いたしました。
地元の方からの一報をいただき、状況を確認後、警察へ被害届を提出いたしましたが、未だ誰が何のためにこのようなことをしたのかはわかっておりません。
この事件の現場検証に来て下さった若い警察官も、「まったく、バチあたりなことをするやつがいるもんですね。」と溢されていましたが、もう一人の警察官が「犯人にはどんなバチがあたるんですかねぇ?」と私に言いました。
それを聞いて私は、大学時代にご指導いただいたある僧侶の先生の言葉がふと頭に浮かびました。
その言葉とは、『仏様は人にバチなんかあてない、人間を懲らしめてやろうなんて仏様は考えないからな。』というものでした。
しかし、当時学生で若かった私は、「それじゃあ、バチは誰があてるんですか?」と先生に聞き返しました。
すると、『バチは誰かがあてるんじゃなく、たいていは自分からバチにあたってるんだよ、人が傷つくことをしたり、もったいないこと、人の道に外れたことをしていると、自分の行く手にバチが置かれてるもんだ。』と答えて下さったのです。
先生のこの言葉を思い出した私は、得意になって『バチは誰かがあてるもんじゃありませんよ…』と、先生と同じ言葉でもって警察の方にお話しをしてしまいました。
人間裸一貫で生まれてきて、いきなりバチに当たる人はいません。
育っていく過程で、先に進んでいく中で、バチの置かれている道を歩くか、バチのない道を歩くか決まってくるものだと思います。
せっかく、仏様からご先祖様からいただいたこの人生、自ら選ぶことができる道もあるのですから、お互いに〝バチ〟には気をつけて、より良い道を進みたいものです。
また、凶悪な事件のニュースを聞く度に、この社会から〝バチ〟に自ら当たりにいくような人が少しでも減り、より良い世界になって欲しいと願わずにはいられません。
年頭に当たり、皆さまのご健勝、ご多幸をせつにお祈りいたします。
-
最近の投稿
-
アーカイブ
- 令和8年1月 (1)
- 令和7年7月 (1)
- 令和7年3月 (1)
- 令和7年1月 (1)
- 令和6年3月 (1)
- 令和6年1月 (1)
- 令和5年8月 (1)
- 令和5年3月 (1)
- 令和5年1月 (1)
- 令和4年12月 (1)
- 令和4年3月 (1)
- 令和4年1月 (1)
- 令和3年8月 (1)
- 令和3年3月 (1)
- 令和3年1月 (1)
- 令和2年7月 (1)
- 令和2年3月 (1)
- 令和2年1月 (1)
- 令和元年7月 (1)
- 平成31年3月 (1)
- 平成31年1月 (1)
- 平成30年7月 (1)
- 平成30年3月 (1)
- 平成30年1月 (1)
- 平成29年7月 (1)
- 平成29年1月 (1)
- 平成28年7月 (1)
- 平成28年3月 (1)
- 平成27年7月 (1)
- 平成27年3月 (1)
- 平成27年1月 (1)
- 平成26年8月 (1)
- 平成26年1月 (1)